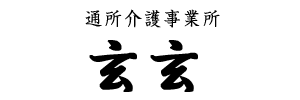サービス内容
「玄玄は、1日の利用定員が最大18名の小さなデイサービスです。
ご利用者お一人おひとりの状態や気分に合わせて、食事・入浴・排泄などの介助やレクリエーションを丁寧に提供しています。
利用者数が限られているからこそ、毎日の小さな変化にも職員全員で気づき、声をかけ合いながらきめ細かな対応が可能です。
その日の“その人らしさ”を大切にしながら、無理なく、心地よく過ごせる時間をつくる──それが玄玄のケアのかたちです。」
サービス提供時間
玄玄のサービス提供は通いの日中のみです(夜間サービスはありません)。
営業日:月曜〜土曜(祝日を除く)
定休日:日曜・祝日。
玄玄で提供している主なサービス
- ご自宅〜玄玄の送迎
- 到着時の健康チェック(バイタル測定等)
- 入浴の介助
- 食事の提供と見守り
- 排泄の介助
- 機能訓練(簡単な体操やリハビリ)
- レクリエーションの企画・実施(季節の遊び、体を動かす活動 等)
医療・介護の専門職による、安心のケア体制
玄玄では、ご利用者さまの健康と安全を守るため、以下のような専門職によるサポート体制を整えています。
玄玄で提供している主なサービス
- 看護師が常勤し、健康管理から緊急対応まで安心を支援。
毎朝のバイタルチェック(体温・血圧など)や服薬管理、緊急時には迅速に医療機関と連携しています。 - 介護福祉士など有資格者が、日々のケアにあたります。
入浴介助、食事・排泄などの身体介助からレクリエーションの実施まで、安心と尊厳を守るケアを行います。 - 少人数だからこそ、スタッフ一人ひとりの変化に気づける体制です。
1日最大18名という小規模な環境であるため、利用者さま一人ひとりの表情や体調の微妙な変化もしっかり把握できます。 - スタッフのスキルアップを積極的にサポート。
定期研修の受講や資格取得を奨励しており、新人には経験豊富な先輩がマンツーマンで指導。安全で確実なケアの提供を通じて、サービスの質を常に高めています。 - 認知症ケアへの配慮にも、常に「そばにいる」
玄玄では、「住み慣れた地域で、いつまでも暮らしたい」という想いを大切にした認知症ケアを心がけています。 - 否定せず、ゆっくり話をお聞きします。
認知症の方が発する「今の気持ち」を大切にし、その人らしさを尊重した対応をします。 - できることは尊重し、できないところは支えるケアを。
「できることは自分で」「できにくいところはそっとサポート」のバランスで、安心感を感じていただける支援を行います。 - 不安な状況には、見守りを強化します。
徘徊などが心配な方には、その日の体調や状態に応じてスタッフの配置や声かけを調整し、安全に配慮した環境づくりに努めています。
このような取り組みを通じて、どんなに小さな変化にもすぐに気づける、身近で温かなケアを提供しています。
INSTAGRAM
Facebook

820
通所介護事業所玄玄
広島市南区東雲二丁目7番17号の地域密着型「通所介護事業所 玄玄」です。
生活とリハビリがつながる介護をめざしています。
スタッフ募集あり(応募はハローワーク:事業所番号3414-616460-5)。
社一帯がパワースポットとなっております。
Japanese real underground CARE organiz
■介護が「社会の仕事」である、という言い回しを、たぶん、私は何度か聞いたことがある。が、それを聞くたびに、うっすらとした違和感のようなものが残る。「社会の仕事」って何だろう。いや、それ以前に「社会」って何なんだ?という疑問も湧いてくる。ここでいう「社会」は、たぶん「国家」や「制度」のことを意味しているのだと思うけど、そう簡単に一義的に整理されるものでもない。「社会の仕事」とは、要するに「家族の責任じゃありません」ということを、やや大げさに言い換えてるだけなのかもしれない。![]() ■それはそれで必要な流れだった。ある時期までは、介護という営みは圧倒的に「家の中」で、「家族」の手で、「無償」でなされていた。介護休暇制度もなければ、デイサービスも訪問介護もなかった時代。たとえばおばあさんが寝たきりになったら、長男の嫁、もしくは長女などがつきっきりでみるしかなかった。そういう「自然な姿」が、昭和の家族には当然のようにあった。そこに「介護の社会化」という魔法の言葉がやってきて、私たちをある意味では一時的に救ったのだと思う。
■それはそれで必要な流れだった。ある時期までは、介護という営みは圧倒的に「家の中」で、「家族」の手で、「無償」でなされていた。介護休暇制度もなければ、デイサービスも訪問介護もなかった時代。たとえばおばあさんが寝たきりになったら、長男の嫁、もしくは長女などがつきっきりでみるしかなかった。そういう「自然な姿」が、昭和の家族には当然のようにあった。そこに「介護の社会化」という魔法の言葉がやってきて、私たちをある意味では一時的に救ったのだと思う。![]() ■でも、この魔法は長くは続かなかった。制度としての「社会化」が進むにつれて、今度は「家族の無関心」が問題になった。ちょっと、あまりに見事な皮肉ではないか。制度化したはずの介護が、再び現場で「家族の関与が薄い」という理由で評価を下げられる。わからない。ほんとに、わからない。制度に任せると決めたのに、「あなた、もっと家族として関わりなさい」と言われる。まるで、片思いの告白をしたら「友達として見てたのに」と言われる中学生みたいな気分である。いや、ほんと。
■でも、この魔法は長くは続かなかった。制度としての「社会化」が進むにつれて、今度は「家族の無関心」が問題になった。ちょっと、あまりに見事な皮肉ではないか。制度化したはずの介護が、再び現場で「家族の関与が薄い」という理由で評価を下げられる。わからない。ほんとに、わからない。制度に任せると決めたのに、「あなた、もっと家族として関わりなさい」と言われる。まるで、片思いの告白をしたら「友達として見てたのに」と言われる中学生みたいな気分である。いや、ほんと。![]() ■そんなこんなで、今日も私は現場で仕事をしている。昔、ある朝、愛する妻と仕事に向かうの車の中、通り沿いにある美容院の名前について、彼女がぼんやりと聞いてきたことがある。「ねぇ、Jah(ジャー)って何?」。私もまた、ぼんやりと呟いて答えた。「神だけど、神じゃない。敬意のかたまりみたいなもん」。なんとなく言った自分のコトバが、それが妙に自分の腑に落ちて、私の中でずっと残っている。介護、いやお年寄りも同じように、どこかで「神じゃないけど、敬意のかたまり」みたいなものであるべきじゃないかと、その時からなんとなく思っていた。
■そんなこんなで、今日も私は現場で仕事をしている。昔、ある朝、愛する妻と仕事に向かうの車の中、通り沿いにある美容院の名前について、彼女がぼんやりと聞いてきたことがある。「ねぇ、Jah(ジャー)って何?」。私もまた、ぼんやりと呟いて答えた。「神だけど、神じゃない。敬意のかたまりみたいなもん」。なんとなく言った自分のコトバが、それが妙に自分の腑に落ちて、私の中でずっと残っている。介護、いやお年寄りも同じように、どこかで「神じゃないけど、敬意のかたまり」みたいなものであるべきじゃないかと、その時からなんとなく思っていた。![]() ■制度とか、社会化とか、合理化とか、いろいろある。でも、結局「目の前の人をどう見るか」という問いに戻ってしまう。そこに、答えはない。「正解」なんて存在しない。ただ、問いがあるだけ。しかも、毎日変わる。朝の表情と、昼の表情と、夕方の表情では、必要なケアが違っている。その変化にどれだけ付き合えるか。それが「介護」であって、「制度」はそのための道具に過ぎない。
■制度とか、社会化とか、合理化とか、いろいろある。でも、結局「目の前の人をどう見るか」という問いに戻ってしまう。そこに、答えはない。「正解」なんて存在しない。ただ、問いがあるだけ。しかも、毎日変わる。朝の表情と、昼の表情と、夕方の表情では、必要なケアが違っている。その変化にどれだけ付き合えるか。それが「介護」であって、「制度」はそのための道具に過ぎない。![]() ■「介護の社会化」は、必要なステップだった。でも、それはあくまで「スタート地点」であって、「ゴール」ではない。むしろ今は、その言葉を一度解体して、もう一度つくりなおす時期に来ているように思う。ケアを「国家」に預けたのではなく、「生活」の中に取り戻す。そのために、玄玄という場がある。地域で人と人が関係を編み直す、その現場として、静かに今日もドアが開いている。介護とは、社会から生活へ、そして再び生活から社会を問い直す営みなのかもしれない。
■「介護の社会化」は、必要なステップだった。でも、それはあくまで「スタート地点」であって、「ゴール」ではない。むしろ今は、その言葉を一度解体して、もう一度つくりなおす時期に来ているように思う。ケアを「国家」に預けたのではなく、「生活」の中に取り戻す。そのために、玄玄という場がある。地域で人と人が関係を編み直す、その現場として、静かに今日もドアが開いている。介護とは、社会から生活へ、そして再び生活から社会を問い直す営みなのかもしれない。![]() 藤渕安生
藤渕安生![]() #玄玄 #デイサービス玄玄 #通所介護 #デイサービス #広島市南区 #広島介護 #介護の社会化 #家族介護 #生活支援 #制度と現場 #介護を考える #介護と音楽 #地域共生 #ケアの本質 #介護のこれから #レゲエと介護
#玄玄 #デイサービス玄玄 #通所介護 #デイサービス #広島市南区 #広島介護 #介護の社会化 #家族介護 #生活支援 #制度と現場 #介護を考える #介護と音楽 #地域共生 #ケアの本質 #介護のこれから #レゲエと介護
■足台について考える。足台、つまり足を置く台である。これ以上でも以下でもない。ただ、介護の現場でそれを「置くべきか否か」「使うか否か」という議論は意外と深い。実は、この足台問題、かなり根が深い。たとえば、椅子に座ったときに足がぶらぶらしているお年寄りの姿を見たことがあるだろうか?あれ、実はけっこう重大なことなのだ。足が床につかない状態は、骨盤が後傾し、姿勢が崩れる。それは呼吸に影響し、咀嚼や嚥下にも波及し、やがて「なんだか元気が出ない」という、うっすらした不調、ひどい場合は誤嚥しそれが肺炎へとつながる。![]() ■足が床につかないと、身体の重心が不安定になる。そうなると座っていること自体が疲れる。リラックスできず、会話や活動への参加意欲も低下する。つまり「足がついているか」という些細に見える条件が、その人の一日の“調子”を決定づけてしまうことがあるのだ。しかも、この状態は本人の意識にのぼりにくい。なんだかだるい。なんだか調子が悪い。でも、どこが原因かわからない。そういう“なんだか”の正体が、足台の不在である可能性もあるわけで。
■足が床につかないと、身体の重心が不安定になる。そうなると座っていること自体が疲れる。リラックスできず、会話や活動への参加意欲も低下する。つまり「足がついているか」という些細に見える条件が、その人の一日の“調子”を決定づけてしまうことがあるのだ。しかも、この状態は本人の意識にのぼりにくい。なんだかだるい。なんだか調子が悪い。でも、どこが原因かわからない。そういう“なんだか”の正体が、足台の不在である可能性もあるわけで。![]() ■そういえば、昔「台に乗る」という行為に妙な憧れがあった。ちょっと背が届かない場所に、踏み台を置いてのぼる。世界が一段違って見える。今回の話とは関係ないけど。ちなみに、またまた全然関係ないが私は子ども時代に、土砂降りの雨の中、自動販売機に模した落書きをした段ボールを道端に置き、一日中その中で過ごしたことがある。そのときは台の上じゃない、段ボールの中だった。知らない子どもがドンジャラのコインを入れてくれたけど、私は何も出すものを持っていなかった。
■そういえば、昔「台に乗る」という行為に妙な憧れがあった。ちょっと背が届かない場所に、踏み台を置いてのぼる。世界が一段違って見える。今回の話とは関係ないけど。ちなみに、またまた全然関係ないが私は子ども時代に、土砂降りの雨の中、自動販売機に模した落書きをした段ボールを道端に置き、一日中その中で過ごしたことがある。そのときは台の上じゃない、段ボールの中だった。知らない子どもがドンジャラのコインを入れてくれたけど、私は何も出すものを持っていなかった。![]() ■で、話を戻すと、足台というのは「地面に自分の足がつく」ことを保障する装置なのだ。これはたとえば「その人がこの場にちゃんと存在している」ということの、静かで、しかし強い証明である。つまり足台とは、物理的にはただの台でも、「その人がその人らしく座るための、思想的な装置」なのではないか。だれの体にも合う椅子など存在しない。だからこそ、椅子に人を合わせるのではなく、人に椅子を合わせる。その調整のために足台がある。足が地面についている。これは介護の本当の基本である。
■で、話を戻すと、足台というのは「地面に自分の足がつく」ことを保障する装置なのだ。これはたとえば「その人がこの場にちゃんと存在している」ということの、静かで、しかし強い証明である。つまり足台とは、物理的にはただの台でも、「その人がその人らしく座るための、思想的な装置」なのではないか。だれの体にも合う椅子など存在しない。だからこそ、椅子に人を合わせるのではなく、人に椅子を合わせる。その調整のために足台がある。足が地面についている。これは介護の本当の基本である。![]() ■ところがこの足台、「なくても別に困ってないですよ」という人が多い。あるいは、「あった方がいいのはわかるけど、邪魔になるし」という声。たしかにそうだ。足台は場所を取る。蹴っ飛ばして転倒するリスクもある。衛生管理も地味に面倒くさい。けれど、そこにはある種の「見えなさ」が関係していると思う。つまり、目の前で本人が困っていなければ、その必要性が見えにくい。あるいは、その不調が「足がついてないこと」に起因しているとは、ほとんど誰も思わない。
■ところがこの足台、「なくても別に困ってないですよ」という人が多い。あるいは、「あった方がいいのはわかるけど、邪魔になるし」という声。たしかにそうだ。足台は場所を取る。蹴っ飛ばして転倒するリスクもある。衛生管理も地味に面倒くさい。けれど、そこにはある種の「見えなさ」が関係していると思う。つまり、目の前で本人が困っていなければ、その必要性が見えにくい。あるいは、その不調が「足がついてないこと」に起因しているとは、ほとんど誰も思わない。![]() ■この“見えなさ”に敏感であること。それこそが、介護の本質のひとつではないかと思う。見えない不調を見つける。見えない負荷を減らす。これは技術ではなく、経験である。そこに気づける経験。そこに注意が向けられる経験。そういう経験則があればこそ、足台が必要かどうか、足台の高さは適切かどうか、といったことにも配慮ができる。だから、足台の話をしているようで、実は「その人を見るということはどういうことか?」という問いを立てているのだ。
■この“見えなさ”に敏感であること。それこそが、介護の本質のひとつではないかと思う。見えない不調を見つける。見えない負荷を減らす。これは技術ではなく、経験である。そこに気づける経験。そこに注意が向けられる経験。そういう経験則があればこそ、足台が必要かどうか、足台の高さは適切かどうか、といったことにも配慮ができる。だから、足台の話をしているようで、実は「その人を見るということはどういうことか?」という問いを立てているのだ。![]() ■ちなみに足台に関しては、素材や高さ、滑り止めの有無なども検討が必要だ。市販品をそのまま使うと、高さが合わなかったり、見た目が「いかにも介護」っぽくて、利用者の気持ちが下がったりすることもある。だから時にはDIYも選択肢に入る。理想は「何も言わなくても、そこに足台があって、ちょうどよく使える」状態だ。それはつまり、「気が利いている環境」ということである。
■ちなみに足台に関しては、素材や高さ、滑り止めの有無なども検討が必要だ。市販品をそのまま使うと、高さが合わなかったり、見た目が「いかにも介護」っぽくて、利用者の気持ちが下がったりすることもある。だから時にはDIYも選択肢に入る。理想は「何も言わなくても、そこに足台があって、ちょうどよく使える」状態だ。それはつまり、「気が利いている環境」ということである。![]() ■介護とは、身体を支えることを通じて、生活を支えることであり、それは「この場所にいていいんだよ」というメッセージでもある。座ったとき、足がしっかりついていると、自然と姿勢が整い、顔が上がり、目線が前に向く。これはその人が、またちょっと“自分”になれたということだ。たかが足台。されど足台。今日、足が浮いていないか、ふと見てみることから、今日のケアは始まるのかもしれない。
■介護とは、身体を支えることを通じて、生活を支えることであり、それは「この場所にいていいんだよ」というメッセージでもある。座ったとき、足がしっかりついていると、自然と姿勢が整い、顔が上がり、目線が前に向く。これはその人が、またちょっと“自分”になれたということだ。たかが足台。されど足台。今日、足が浮いていないか、ふと見てみることから、今日のケアは始まるのかもしれない。![]() ■ちなみに、食事に限らず、トイレに座るときも、足がついてるかどうかはすごく大事です。
■ちなみに、食事に限らず、トイレに座るときも、足がついてるかどうかはすごく大事です。![]() 藤渕安生
藤渕安生![]() #玄玄 #デイサービス玄玄 #通所介護 #デイサービス #広島市南区 #広島介護 #足台のある暮らし #関係性のケア #高齢者の姿勢ケア #見えない不調に気づく #介護の気づき #リハビリと生活 #姿勢調整 #咀嚼嚥下サポート #介護DIY #気づける介護
... See MoreSee Less
#玄玄 #デイサービス玄玄 #通所介護 #デイサービス #広島市南区 #広島介護 #足台のある暮らし #関係性のケア #高齢者の姿勢ケア #見えない不調に気づく #介護の気づき #リハビリと生活 #姿勢調整 #咀嚼嚥下サポート #介護DIY #気づける介護
... See MoreSee Less
■「寮母」という言葉を最近聞かなくなった。![]() そもそも「寮」がないのだろうか。
そもそも「寮」がないのだろうか。![]() いや、ある。でも、言葉として「寮母」が失われつつある。そして、老人ホームの介護職もむかしは「寮母」と呼ばれていた。が、今は言わない、聞かない。なんとこれは、ちょっとした事件なのではないか、と勝手に思っている。ニュースにはならないタイプの、静かな事件である。
いや、ある。でも、言葉として「寮母」が失われつつある。そして、老人ホームの介護職もむかしは「寮母」と呼ばれていた。が、今は言わない、聞かない。なんとこれは、ちょっとした事件なのではないか、と勝手に思っている。ニュースにはならないタイプの、静かな事件である。![]() ■背景には、介護の世界・資格が国家資格化され、専門性が明確になっていったことがあるのだと思う。
■背景には、介護の世界・資格が国家資格化され、専門性が明確になっていったことがあるのだと思う。![]() さらに、男性介護職が増えたことで、ジェンダー中立的な名称として「介護職員」や「ケアワーカー」といった言葉が一般的になっていった。その流れのなかで、「寮母」という言葉は、静かに片隅へと追いやられた。
さらに、男性介護職が増えたことで、ジェンダー中立的な名称として「介護職員」や「ケアワーカー」といった言葉が一般的になっていった。その流れのなかで、「寮母」という言葉は、静かに片隅へと追いやられた。![]() 制度的には洗練されたのかもしれないけれど、言葉のなかにあった“匂い”のようなものが、少しずつ失われていった気もする。
制度的には洗練されたのかもしれないけれど、言葉のなかにあった“匂い”のようなものが、少しずつ失われていった気もする。![]() ■寮母という言葉には、「ケアの本質」みたいなものが、なんとなく、ふわっと、にじんでいる。
■寮母という言葉には、「ケアの本質」みたいなものが、なんとなく、ふわっと、にじんでいる。![]() 職業名というよりは、空気みたいな存在。階段の手すりに触れたときの温度とか、トイレットペーパーの減り具合に気づいて補充してくれている存在とか、そういう“名もなきケア”の象徴だ。
職業名というよりは、空気みたいな存在。階段の手すりに触れたときの温度とか、トイレットペーパーの減り具合に気づいて補充してくれている存在とか、そういう“名もなきケア”の象徴だ。![]() ■今、介護現場に必要なのは、まさにこの「名もなきケア」なのではないかと思っている。
■今、介護現場に必要なのは、まさにこの「名もなきケア」なのではないかと思っている。![]() 排泄介助とか、入浴とか、機能訓練とか、もちろん大事。でも、「そろそろお腹すいてるかもね」とつぶやきながらあなたの傍らに立つ人の存在は、それらと同じくらい、いや、場合によってはそれ以上に重要だ。
排泄介助とか、入浴とか、機能訓練とか、もちろん大事。でも、「そろそろお腹すいてるかもね」とつぶやきながらあなたの傍らに立つ人の存在は、それらと同じくらい、いや、場合によってはそれ以上に重要だ。![]() ■寮母は、“生活をともにする人”だ。
■寮母は、“生活をともにする人”だ。![]() 観察者ではない。支援者でもないかもしれない。もしかすると、「一緒に居てくれる人」くらいの、絶妙な距離感。これはもう、スキルとかではなくて、その人の「在り方」に近い。制度では測れないやつだ。介護保険では単位数がつかない。
観察者ではない。支援者でもないかもしれない。もしかすると、「一緒に居てくれる人」くらいの、絶妙な距離感。これはもう、スキルとかではなくて、その人の「在り方」に近い。制度では測れないやつだ。介護保険では単位数がつかない。![]() ■ちょっと話が飛ぶが、最近ふと気になって、「選挙フェス」、三宅洋平くんが出ていた2013年の参院選の街宣動画をyoutubeで見返した。暑い中、路上でギターを持って、「生活者の感覚」を語っていた。私は彼を応援していた。その10年前、私は宮島の奥地の浜辺で開かれていたまつりにMCで出演していた。そこに、犬式も出ていた。彼と少し話をして、かっこいいなって思っていた。2009年くらい、私は初めて横浜のオムツ外し学会で、お年寄りたちのことをたくさんの写真とともに話した。こんなにお年寄りはすごいんだぞと。その時、写真とともに流した音楽も、犬式だった。私の中では、なんか、うまく言えないんだけど、彼のあの感じ、実は寮母に似てるなと思っていた。これは、女性的とか男性的とか、私の中ではそういうジェンダー的な話ではない。何度も書くが、態度の話だ。
■ちょっと話が飛ぶが、最近ふと気になって、「選挙フェス」、三宅洋平くんが出ていた2013年の参院選の街宣動画をyoutubeで見返した。暑い中、路上でギターを持って、「生活者の感覚」を語っていた。私は彼を応援していた。その10年前、私は宮島の奥地の浜辺で開かれていたまつりにMCで出演していた。そこに、犬式も出ていた。彼と少し話をして、かっこいいなって思っていた。2009年くらい、私は初めて横浜のオムツ外し学会で、お年寄りたちのことをたくさんの写真とともに話した。こんなにお年寄りはすごいんだぞと。その時、写真とともに流した音楽も、犬式だった。私の中では、なんか、うまく言えないんだけど、彼のあの感じ、実は寮母に似てるなと思っていた。これは、女性的とか男性的とか、私の中ではそういうジェンダー的な話ではない。何度も書くが、態度の話だ。![]() 彼は、マイクは握ってるけど、別に煽ってない。主張はあるけど、主導権は渡している。支配じゃなくて、共に居る感じ。これはまさに「寮母力」だとおもっていた。
彼は、マイクは握ってるけど、別に煽ってない。主張はあるけど、主導権は渡している。支配じゃなくて、共に居る感じ。これはまさに「寮母力」だとおもっていた。![]() ■たとえば、デイサービスでいうと、毎日同じ時間にくる方のことを、あるスタッフが、「なんか今日はちょっと違う気がする」と言ったとする。
■たとえば、デイサービスでいうと、毎日同じ時間にくる方のことを、あるスタッフが、「なんか今日はちょっと違う気がする」と言ったとする。![]() その“違う気がする”を言葉にできるかどうかじゃなくて、それを「受け取ってくれる誰か」がいるかどうかが大事なんじゃないか。
その“違う気がする”を言葉にできるかどうかじゃなくて、それを「受け取ってくれる誰か」がいるかどうかが大事なんじゃないか。![]() 「そっか、そんな感じするんだね」と、ただそう言ってくれるだけで、ずいぶんと世界が変わることもある。
「そっか、そんな感じするんだね」と、ただそう言ってくれるだけで、ずいぶんと世界が変わることもある。![]() ■こういう反応を、マニュアルには書けない。書いても、読んだ側はその通りには動けない。
■こういう反応を、マニュアルには書けない。書いても、読んだ側はその通りには動けない。![]() つまり、これは「技術」じゃなくて「態度」の問題なのだ。寮母的な人は、相手をケアする前に、相手と“生きている”。これは技術でなく、関係性の中でしか発揮できないものだ。
つまり、これは「技術」じゃなくて「態度」の問題なのだ。寮母的な人は、相手をケアする前に、相手と“生きている”。これは技術でなく、関係性の中でしか発揮できないものだ。![]() ■思うに、これからのデイサービスには、寮母的なスタッフが必要になる。
■思うに、これからのデイサービスには、寮母的なスタッフが必要になる。![]() 利用者の「生活」を理解しようとする人、生活と生活が重なる場所を作ろうとする人。
利用者の「生活」を理解しようとする人、生活と生活が重なる場所を作ろうとする人。![]() ■残念ながらおそらく今、介護現場には“寮母力”のような曖昧で柔らかい、けれど確かな力が不足している。
■残念ながらおそらく今、介護現場には“寮母力”のような曖昧で柔らかい、けれど確かな力が不足している。![]() 理由は簡単で、「曖昧なものを排除して、効率と正しさで評価する」文化が社会全体に広がっているからだ。そうすると、真っ先に消えていくのは、寮母的な気配の仕事なのだ。
理由は簡単で、「曖昧なものを排除して、効率と正しさで評価する」文化が社会全体に広がっているからだ。そうすると、真っ先に消えていくのは、寮母的な気配の仕事なのだ。![]() ■でも、だからこそ、あえて今、寮母的な力を、もう一度大事にしてみたい。
■でも、だからこそ、あえて今、寮母的な力を、もう一度大事にしてみたい。![]() それは別に「昔は良かった」ではない。「これからを良くするにはどうするか」の話だ。
それは別に「昔は良かった」ではない。「これからを良くするにはどうするか」の話だ。![]() 生活をともにする感覚、生活とリハビリをつなげる感覚。ケアの基本は、たぶん、そこにある。
生活をともにする感覚、生活とリハビリをつなげる感覚。ケアの基本は、たぶん、そこにある。![]() ■介護というのは、支援の提供ではない。生活の共有だ。
■介護というのは、支援の提供ではない。生活の共有だ。![]() そう考えたとき、「寮母力」は、最新の介護理論とつながる。
そう考えたとき、「寮母力」は、最新の介護理論とつながる。![]() 利用者の声を聴くまえに、まずその空間に“居る”こと。黙って、でも注意深く、そしてちょっと笑って。
利用者の声を聴くまえに、まずその空間に“居る”こと。黙って、でも注意深く、そしてちょっと笑って。![]() わたしたちは、寮母のような存在から、関係性のケアを学びなおす必要があるのかもしれない。
わたしたちは、寮母のような存在から、関係性のケアを学びなおす必要があるのかもしれない。![]() 藤渕安生
藤渕安生![]() #玄玄 #デイサービス玄玄 #通所介護 #デイサービス #広島市南区 #広島介護 #寮母力 #名もなきケア #生活支援 #ケアの本質 #三宅洋平 #介護の未来 #介護職あるある #やさしさの価値
... See MoreSee Less
#玄玄 #デイサービス玄玄 #通所介護 #デイサービス #広島市南区 #広島介護 #寮母力 #名もなきケア #生活支援 #ケアの本質 #三宅洋平 #介護の未来 #介護職あるある #やさしさの価値
... See MoreSee Less
■その人は「もう治らない」時間を生きている。けれど、それは決して「終わった時間」ではない。![]() ■病院では「急性期」「回復期」と順に分類されるが、そのあとに続くのが「慢性期」と呼ばれる時間だ。けっこう適当なネーミングだ。言葉の感度がちょっと弱い。なんだか「ずっと続いてるだけ」みたいで、何も起こらなさそう。ほんとうに?
■病院では「急性期」「回復期」と順に分類されるが、そのあとに続くのが「慢性期」と呼ばれる時間だ。けっこう適当なネーミングだ。言葉の感度がちょっと弱い。なんだか「ずっと続いてるだけ」みたいで、何も起こらなさそう。ほんとうに?![]() ■この「慢性期」は、医療の専門用語だが、わたしたちの生活のなかにもこっそり入り込んでくる。たとえば、いつまでも治らない腰痛、雨の日にうずく古傷、ひとり暮らしに慣れすぎた空気。つまり、「このままでいいわけじゃないけど、このままでいるしかない」状態。すこし悲しく、すこし美しい。そんな日々を、介護の現場ではたくさん目にする。
■この「慢性期」は、医療の専門用語だが、わたしたちの生活のなかにもこっそり入り込んでくる。たとえば、いつまでも治らない腰痛、雨の日にうずく古傷、ひとり暮らしに慣れすぎた空気。つまり、「このままでいいわけじゃないけど、このままでいるしかない」状態。すこし悲しく、すこし美しい。そんな日々を、介護の現場ではたくさん目にする。![]() ■最近また、『野生の思考』(レヴィ=ストロース)を読み返していた。あれは昔読んだ時はさっぱりわからなかった。でも、いまでも、ほぼわからない。。でも、「病気は症状だけじゃなく、文化にも関係している」といったことが書いてあって、そのとき、「慢性期って、文化なんじゃないか?」とふと思った。文化は治らない。進化もしない。あれは「生き方」の話だ。
■最近また、『野生の思考』(レヴィ=ストロース)を読み返していた。あれは昔読んだ時はさっぱりわからなかった。でも、いまでも、ほぼわからない。。でも、「病気は症状だけじゃなく、文化にも関係している」といったことが書いてあって、そのとき、「慢性期って、文化なんじゃないか?」とふと思った。文化は治らない。進化もしない。あれは「生き方」の話だ。![]() ■慢性期のケアは、”スピード”も”成果”も、たぶん向いていない。というか、逆効果。話を聞いても、相手がなにも返さないことがある。でもそれでも、そばにいる。「なにか言って」と思うときほど、言葉を投げる側が不安だったりする。この関係性こそがケアの入り口だと思う。
■慢性期のケアは、”スピード”も”成果”も、たぶん向いていない。というか、逆効果。話を聞いても、相手がなにも返さないことがある。でもそれでも、そばにいる。「なにか言って」と思うときほど、言葉を投げる側が不安だったりする。この関係性こそがケアの入り口だと思う。![]() ■かつて「ケア」は「労働」ではなく、「気遣い」、もっと言えば、「おせっかい」だった。さらにさらにもっと言えば「そわそわする感じ」だった。「これ、このままでいいのかな?」と考え続けること。それが介護者にも、要介護者にも、両方にある関係。これって、わたしたちは、「治らない人」の時間に付き添うのではなく、「治らないわたしたち」の関係を続けているのかもしれない。
■かつて「ケア」は「労働」ではなく、「気遣い」、もっと言えば、「おせっかい」だった。さらにさらにもっと言えば「そわそわする感じ」だった。「これ、このままでいいのかな?」と考え続けること。それが介護者にも、要介護者にも、両方にある関係。これって、わたしたちは、「治らない人」の時間に付き添うのではなく、「治らないわたしたち」の関係を続けているのかもしれない。![]() ■医療の世界では、慢性期を「状態が安定した後の時間」と呼ぶことがある。でも、それはほんとうに「安定」なんだろうか。玄玄で利用者さんを見ていると、日々が揺れている。眠そうな日、笑いすぎる日、何も言わない日。どの日も「慢性期」だ。だけど、全部ちがう。つまり、「安定」はしていない。けれど、「関係性」はある。
■医療の世界では、慢性期を「状態が安定した後の時間」と呼ぶことがある。でも、それはほんとうに「安定」なんだろうか。玄玄で利用者さんを見ていると、日々が揺れている。眠そうな日、笑いすぎる日、何も言わない日。どの日も「慢性期」だ。だけど、全部ちがう。つまり、「安定」はしていない。けれど、「関係性」はある。![]() ■ある日、スタッフがぼそっと言った。「◯◯さん、最近ちょっと…“戻ってる”感じがしますね」
■ある日、スタッフがぼそっと言った。「◯◯さん、最近ちょっと…“戻ってる”感じがしますね」![]() 進歩でも後退でもない。「戻る」って、どういうことだろう。その「わからなさ」にこそ、慢性期のヒントがある。
進歩でも後退でもない。「戻る」って、どういうことだろう。その「わからなさ」にこそ、慢性期のヒントがある。![]() ■だからこそ、介護の現場では、「こうすればよくなる」は通用しない。代わりに、「こういうふうに付き合えるかもね」と話し合う。その試行錯誤の繰り返しが、慢性期のケアになる。
■だからこそ、介護の現場では、「こうすればよくなる」は通用しない。代わりに、「こういうふうに付き合えるかもね」と話し合う。その試行錯誤の繰り返しが、慢性期のケアになる。![]() ■言葉が通じなくても、表情がない日でも、あいさつが返ってこなくても。わたしたちは「今日、ここに来てくれた」という事実に向き合っている。そこには「関係性」がある。それは、「よくなった」とか「悪くなった」では測れない、もうひとつの物差しだ。
■言葉が通じなくても、表情がない日でも、あいさつが返ってこなくても。わたしたちは「今日、ここに来てくれた」という事実に向き合っている。そこには「関係性」がある。それは、「よくなった」とか「悪くなった」では測れない、もうひとつの物差しだ。![]() ■玄玄では、この「関係性」をどう積み重ねていくかが問われている。それは記録にも残らないし、マニュアルにも書かれていない。でも、だからこそ大事にしたい。
■玄玄では、この「関係性」をどう積み重ねていくかが問われている。それは記録にも残らないし、マニュアルにも書かれていない。でも、だからこそ大事にしたい。![]() ■慢性期とは、「終わらない時間」ではない。「わたしたちが関係を続けていく時間」だ。ケアとは、その関係をほどかず、寄り添う技術である。成果や回復を求めるよりも、「今日はこんな感じだったね」と言える関係こそが、慢性期ケアの土台になるのだとおもっている。
■慢性期とは、「終わらない時間」ではない。「わたしたちが関係を続けていく時間」だ。ケアとは、その関係をほどかず、寄り添う技術である。成果や回復を求めるよりも、「今日はこんな感じだったね」と言える関係こそが、慢性期ケアの土台になるのだとおもっている。![]() 藤渕安生
藤渕安生![]() #玄玄 #デイサービス玄玄 #通所介護 #デイサービス #広島市南区 #広島介護 #慢性期ケア #関係性のケア #介護観 #レヴィストロース #文化としての介護 #日常のリズム #介護の哲学 #介護現場の声 #介護職と価値観
... See MoreSee Less
#玄玄 #デイサービス玄玄 #通所介護 #デイサービス #広島市南区 #広島介護 #慢性期ケア #関係性のケア #介護観 #レヴィストロース #文化としての介護 #日常のリズム #介護の哲学 #介護現場の声 #介護職と価値観
... See MoreSee Less
アクセス
住 所 :広島市南区東雲2丁目7番17号